メンバー
日米先端工学 (JAFOE) シンポジウムとは
【概要と特色】
全米工学アカデミー(NAE)と日本工学アカデミー(EAJ)の共催によるシンポジウムで、過去12回の実績を有する。通称の“JAFOE”はJapan America Frontiers of Engineeringの略である。日米両国の若手研究者(30~45歳程度)約30名ずつ計約60名が一堂に会し、3日間にわたり最先端工学分野の4つのテーマ(毎回新規に設定される)について発表・討議を行なう。学会などが主催する通常のシンポジウムに比べて次のような特色を有する。
- 異なる4分野の発表・討議すべてに全参加者が出席する異分野交流の場である。
- 厳選された若手研究者のみにより、制約のない自由活発な討議を行なう。
- 企画・運営も若手研究者によって行なわれる。
- 発表者・討議者は主に、企画・運営に携わる若手研究者によって選ばれる。ただしそれとは別に EAJ などが選出する研究者若干名も加わる。
【期待される成果】
- 異分野や分野横断的な最先端技術を議論することにより、通常では得られない知的刺激を受け、新しい研究開発の着想を生む場となる。
- 会期中全員が共同研究行動を共にすることにより、若手研究者間の親密なネットワークが形成され、分野横断的な共同研究や新技術の移転が促進される。
- 企画・運営に携わる若手研究者にとっては、研究リーダーとしてのマネジメント能力を高める場となる。
【これまでの経緯】
NAEは1995年以来、若手研究者間の議論の場として“FOE”(Frontiers of Engineering)を開催し成果を得てきたが、さらにそれを国際的な規模に広げ、1998年には独米間で二国間シンポジウムを発足させた。ついでNAEより日米両国間で同様なシンポジウムを行う提案があり、科学技術振興事業団(現国立研究開発法人科学技術振興機構 JST)が主体となり、EAJがこれに協力する形で、2000年11月に日本で第1回が開催された。第2回は911テロ事件のため米国開催が不能となり、翌2002年に日本で行われた。以後は毎年米国と日本で交互に開催され、2009年に米国で第9回を実施した。なおこれを機に、日本側運営主体は、JSTからEAJに代わり、JSTは引き続き本事業を資金的側面から支援することになった。
一方、FOE は世界的にも注目される若手育成プログラムとなり、NAEは国内およびドイツ、日本との実施に加え、中国、インド、EU、ブラジルなどとも行うことが決まり、各国との開催頻度の調整が必要になった。日米間については、2011年に第10回(日本)、2012年に第11回(米国)で開催した後、2014年の第12回(日本)より隔年で開催することになった。
【運営方法】
日米双方において、運営委員長各1名、運営委員各4名(テーマごとに各1名)が、毎回新規(再任も可)に選出され、企画・運営にあたる。シンポジウムに参加する発表者、招待討議者は下に示すように選出される。
NAEおよびEAJは運営委員長の人選を行い、その活動が円滑に運ぶよう支援する。また必要な資金を調達する。
- 運営委員長(Co-chair)は、企画・運営を統括する責任者となる。NAE、EAJの助言を得つつ、日米Co-chair間の協議のもとに、4テーマと各4名の運営委員を決定する。
- 運営委員(Organizer)は、担当テーマのセッションについて構想を練り、発表テーマと発表者を選定し、セッションプログラムの作成にあたる。シンポジウム当日はセッションチェアを務める。運営委員についてはさらに詳細を6項に記す。
- 発表者(Speaker)は、セッションごとに日米各2名が運営委員によって選出され、発表および討論を行い、後述するポスターセッションにも参加する。
- 招待討議者(General Participants)は日米運営委員が2名ずつ選出するテーマを専門とする招待討議者と主催組織などによって選出されるテーマを専門としない招待討議者から構成され、討論およびポスターセッションに参加する。
【開催形態】
シンポジウムは、日米約30名、計約60名の参加者が一堂に会し、3日間を通し4つのセッションについて、1つの会場で討論を行う形態をとる。使用言語は英語。1つのセッションは3時間で、日米各2名の発表者1人あたり20~30分の発表と、それに対する討論より構成される。参加者はすべのセッションに出席し、積極的に討論に参画することが要請される。
研究者間の交流促進の一環として、4つのセッションとは別に、参加者全員(運営委員長、運営委員も含む)が各自の研究成果をポスター展示し、所定のポスターセッション時間帯では各自がその説明・質疑応答にあたる。
その他、会期中に近傍の研究開発施設の見学、著名人による特別講演なども行われる。
日本においては、シンポジウムの2~3ヶ月前に、参加者が日本語で事前発表する会を設け、発表内容に対する理解を深めるとともに、参加者や関係者間の相互理解と連携強化の一助とする。またシンポジウム終了後に、参加者以外の関係者も招いて報告会を行う。
※ 米国工学アカデミーによるFOEサイトもご参照ください。( NAE (National Academy of Engineering) はこちら)
【日本側運営委員について】
・運営委員の役割
- 4テーマのうちの1つを担当し、米国側の同テーマ担当のOrganizerと連絡をとり、また運営委員長やEAJ関係者などとも連絡をとりながら、セッション全体の構想を纏めてプログラムを作成し、それに相応しい発表者2名、招待討議者2名を選定し、それぞれに参加を依頼し承諾を得るところまで行なう。
- シンポジウム当日はセッションチェアを務め、セッションの最後にセッションサマリーを行う。また事前勉強会及び事後報告会においても、セッションの代表として必要な発表・報告を行なう。
- 運営委員長、他の運営委員、EAJ関係者などとも連携を密にし、シンポジウム全体の企画、推進、実行に貢献する。
・選任条件
- 担当テーマの研究開発状況に通暁し、国内産官学若手研究者(45歳以下)の動向に詳しく、発表者・招待討議者候補者に趣旨を説明して参加依頼できること。
- 下に示す活動期間中相応の時間と労力を割くことが可能であり、シンポジウムや事前・事後の会合等に出席できること。
- 自身も45歳程度以下であること。
- 米国側OrganizerやNAEスタッフとメールや電話会議で意見交換する必要があり、当日も英語でセッションチェアを務めることから、相応の英語力が必要とされる。
・活動期間と活動内容
- 選任後2-3ヶ月: セッションの構想をまとめ、発表者、招待討議者を確定する。
この作業が最も重要である。 - 1終了後事前勉強会まで: シンポジウムの2-3ヶ月前に実施する予定の事前勉強会(仮称)に向けての準備と当日の出席。
- 2終了後当日まで: シンポジウムに向けての準備と当日の出席。
- シンポジウム終了後数ヶ月以内: 事後報告会への出席。
最新の活動報告
下記の通り第17回 JAFOEシンポジウムを開催いたしました。 [新着]
お知らせ
第17回日米先端工学(JAFOE)シンポジウム報告
- 開催期日: 2025年6月1日~4日(6月1日ウェルカムレセプション)
- 開催場所: 米国カリフォルニア大学サンディエゴ校 Jacobs School of Engineering
- 運営委員長:
日本側 所千晴 早稲田大学・東京大学教授・EAJ会員
米国側 Prof. Christopher A. Schuh MIT Northwestern University教授 - テーマおよび運営委員:(順不同)
(1) Resurgence in Fusion Science and Engineering
藤岡 慎介(大阪大学レーザー研究所 教授)
Alessandro Marinoni(カリフォルニア大学San Diego校 助教)
(2) Heterogeneous Integration in Semiconductors
百瀬 健(熊本大学教授)
Qing Cao (イリノイ大Urbana Champaign校准教授)
(3) Clinical-Grade Wearable Sensors
三宅 丈雄(早稲田大学教授)
Canan Dagdeviren (マサチューセッツ工科大助教)
(4) Sustainable Ocean Engineering
長谷川 洋介(東京大学生産技術研究所教授)
Michael Lawson (国立再生可能エネルギー研究所グループマネージャー) - シンポジウムプログラム
- 参加者名簿
- 日本人参加者による事前勉強会
- 報告書
【国内協賛パートナー】
| 協賛A | 東レ株式会社 |
| 協賛B | IHI運搬機械株式会社 MDPI 鹿島建設株式会社 富士フイルム株式会社 |
主催:公益社団法人日本工学アカデミー(EAJ)
米国工学アカデミー(NAE)
共催:科学技術振興機構(JST)
これまでの活動
過去のJAFOEシンポジウム
| 第17回 2025.6.1-4 San Diego |
Resurgence in Fusion Science and Engineering Heterogeneous Integration in Semiconductors Clinical-Grade Wearable Sensors Sustainable Ocean Engineering |
| 第16回 2023.7.18-20 東京 |
Materials by Design Computational Approaches to Address Infectious Diseases The Arduous and Exciting Path to the Development of Successful Mobility Exoskeletons Circular Economy |
| 第15回 2021.6.24-26 オンライン開催 |
Blockchain Technology Soft Robotics “Advanced AI” Mitigating Sea Level Rise Machine Learning for Mental Health |
| 第14回 2018.6.17-20 茨城 |
The Water Treatment Revolution Advanced AI Bionics and Prosthetics Smart Structures and Materials |
| 第13回 2016.6.16-18 Irvine |
Additive Manufacturing Virtual-Physical Processes Big Data Nanotechnology in Energy Storage and Conversion Urban Mobility Efficiency |
| 第12回 2014.6.9-11 東京 |
Bioimaging Power Unplugged: Energy Harvesting and Power Transmission Noise Control Engineering in Healthcare Environments Field Robotics for Disaster Response |
| 第11回 2012.10.29-31 Irvine |
Engineering for Natural Disaster Resiliency Engineering for Agriculture Video Content Analysis Sports Engineering |
| 第10回 2011.6.6-8 大阪 |
Massive Data Management Smart Grid Bio-inspired Materials Robotics |
| 第9回 2009.11.9-11 Irvine |
Breakthrough Technologies in Brain Science Modeling Global Climate Change Novel Materials for Industrial Applications State-of-the-Art Technologies for Knowledge Management ※プログラム詳細は科学技術振興機構(JST)HPをご参照ください |
| 第8回 2008.11.17-19 神戸 |
Advances in Automation and Instrumentation for Biotechnology and Healthcare The Future of Sequence Modeling Alternative Energy Advanced Sensor Technology ※プログラム詳細は科学技術振興機構(JST)HPをご参照ください |
| 第7回 2007.11.5-7 Palo Alto |
Human-Computer Interaction Battery Technologies Rocketry/Aerospace Materials for Medicine ※プログラム詳細は科学技術振興機構(JST)HPをご参照ください |
| 第6回 2006.11.9-11 つくば |
Cybersecurity Biomechatronics Systems Biology Organic Electronics ※プログラム詳細は科学技術振興機構(JST)HPをご参照ください |
| 第5回 2005.11.3-5 San Jose |
Humanoid Robots Pure Water Technologies Semiconductor R&D Biotechnology: Detection and Destruction of Pathogens ※プログラム詳細は科学技術振興機構(JST)HPをご参照ください |
| 第4回 2004.11.4-6 京都 |
Biomedical Instrumentation and Devices IT for the Elderly Optical Communications Hydrogen Energy ※プログラム詳細は科学技術振興機構(JST)HPをご参照ください |
| 第3回 2003.11.20-22 Irvine |
Large-Scale Civil Systems Electrifying the 21st Century Systems Biology and the Emerging Discipline of Biological Engineering Multimedia Networking ※プログラム詳細は科学技術振興機構(JST)HPをご参照ください |
| 第2回 2002.10.24-26 東京 |
Bioengineering Synthesis and Applications of Nanomaterials Sustainable Manufacturing Pervasive Computing ※プログラム詳細は科学技術振興機構(JST)HPをご参照ください |
| (2001年度は911テロ事件のため米国開催が中止となった) | |
| 第1回 2000.11.2-4 奈良 |
Earthquake Engineering Design and Integration of Functional Inorganic Materials Manufacturing Biotechnology ※プログラム詳細は科学技術振興機構(JST)HPをご参照ください |

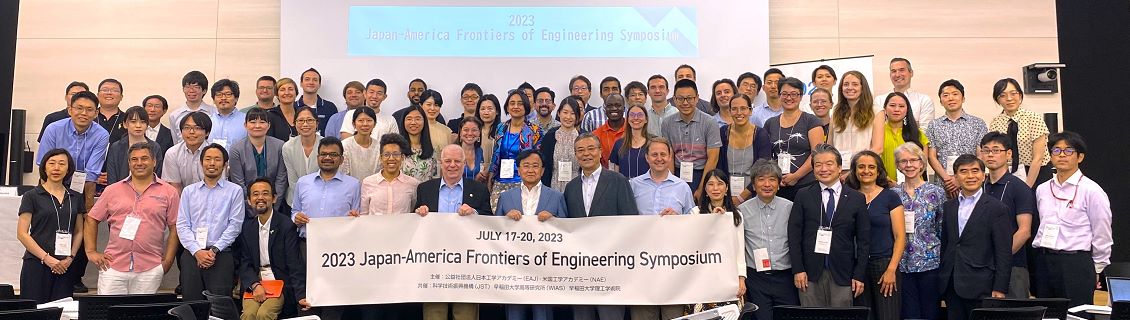
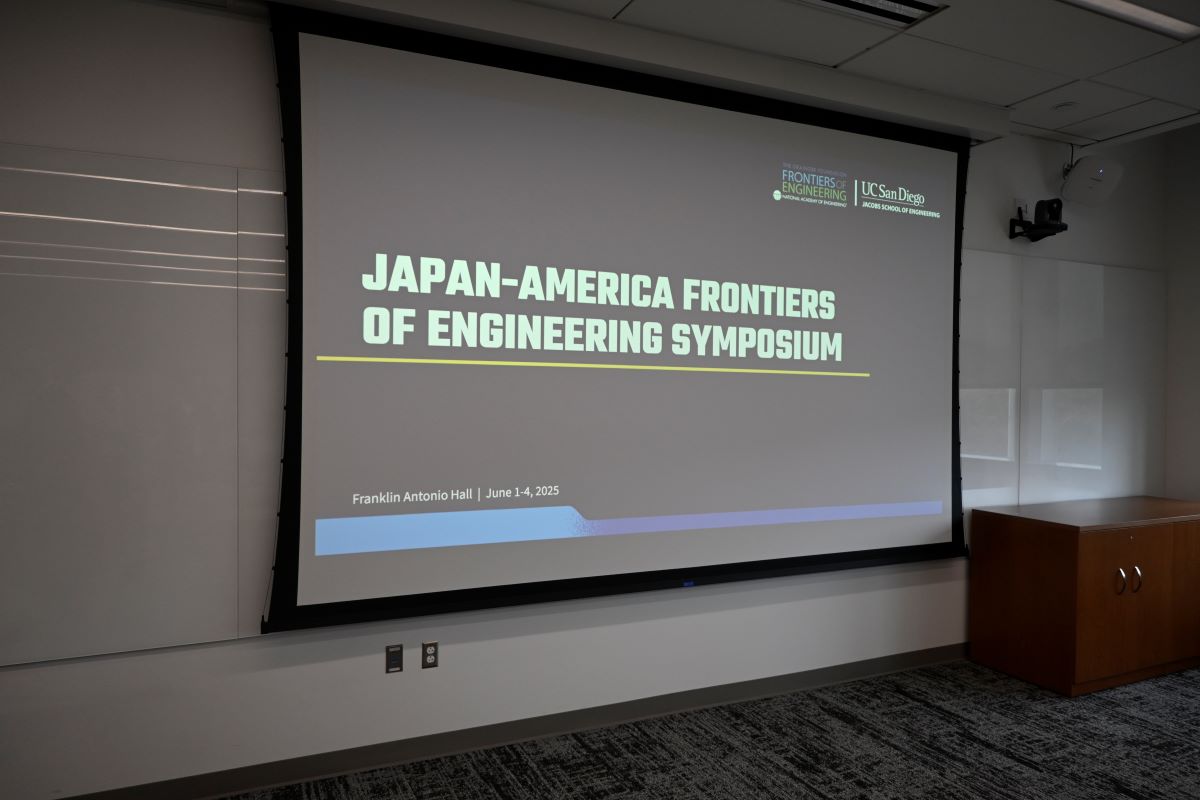
















 Best Speaker Award
Best Speaker Award Best Speaker Award
Best Speaker Award Most Interactive Person’s Award
Most Interactive Person’s Award Most Interactive Person’s Award
Most Interactive Person’s Award